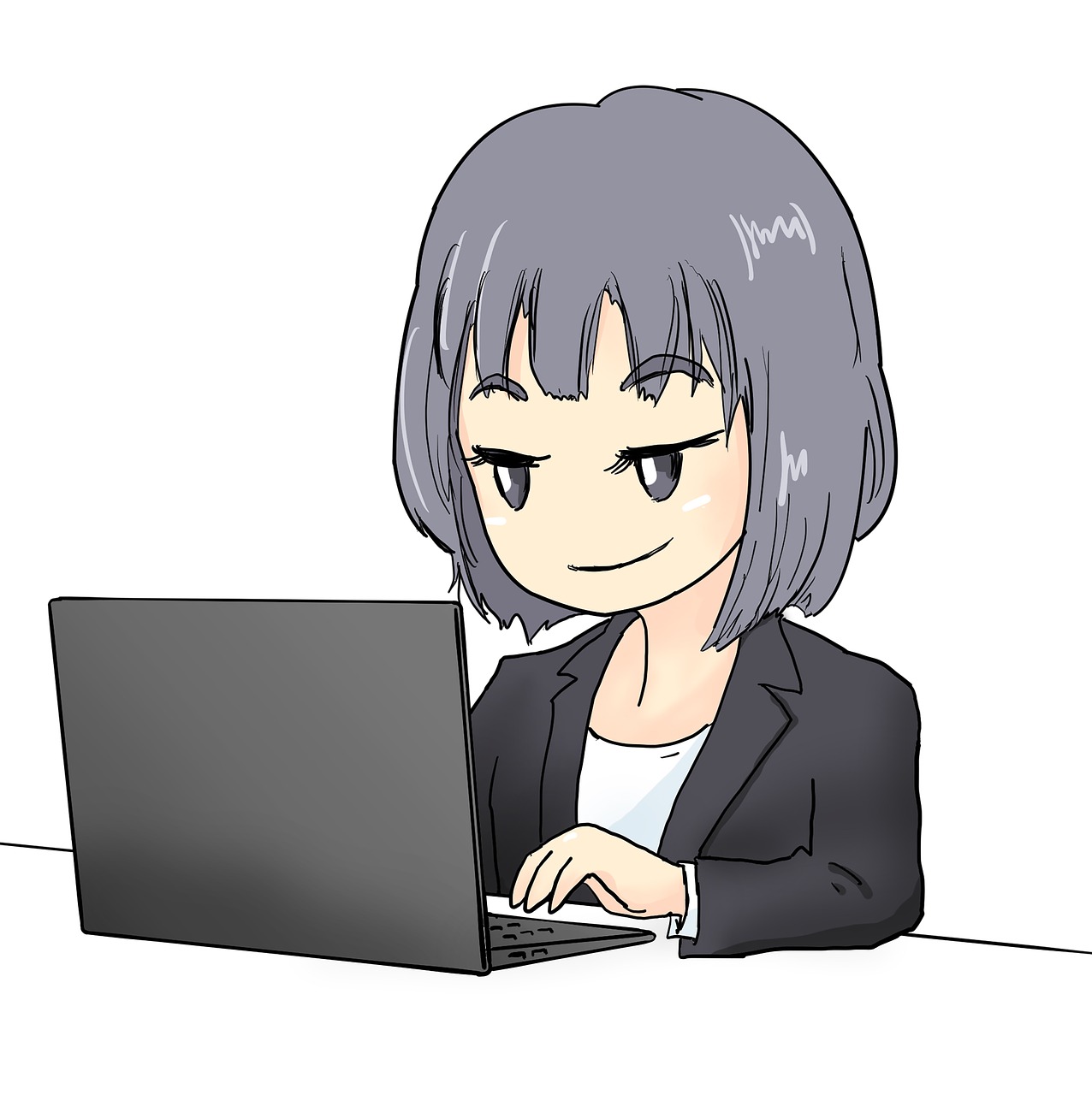ビル管理士資格試験用の「メモ5」は、「給水・排水の整備」編です。
出題数は35問(全180問)。
足きりの40%は14問です。
「給水・排水の整備」への対策
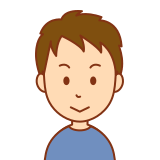
出題数も35問と多いですし、普段の仕事で馴染みのある分野ですので、高得点を狙いたい分野です。
「ビル管理士要点まとめ」へのリンクを貼っておきます。
給排水の用語と単位
給排水の用語
- オフセット :配水管が平行移動している部分
- 活性汚泥 :好気微生物の集合体
- スカム :排水槽内の浮上物質
- 逃し通気管 :排水系統に生じた圧力を逃すための管
- 二重トラップ :配水管に直列に配置された2つのトラップ。排水が阻害されるので禁止
- バイオフィルム:微生物による膜
- バルキング :活性汚泥が単位重量当りの体積が増加して沈降しにくくなる現象
- ブランチ間隔 :垂直距離が2.5mを超える排水立て管の間隔 ※意味不明・丸暗記
給排水の単位
- 加熱能力 :KW
- 水槽内照度率 :%
- ばっき槽混合液浮遊物質濃度(MLSS) :mg/L
- 比体積 :m3/kg
- 密度 :kg/m3
- 比熱の単位 :J/(g・℃) または J/(g・k)
- BOD容積率 :kg/(m3・日)
水道水の塩素消毒
- 次亜塩素酸や次亜塩素酸イオンの遊離残留塩素が消毒効果を表す
- DPD法は、遊離残留塩素 → 結合残留塩素 の順で発色
- 消毒効果の比較 :次亜塩素酸 > 次亜塩素酸イオン > ジクロラミン > モノクロラミン
- 塩素消毒の効果の影響 :PHの影響を受ける。アルカリ性側で消毒効果が急減。窒素化合物と反応すると減少。
- 塩素濃度と接触時間 :微生物を不活性化させる塩素濃度と接触時間は反比例の関係。CT値=塩素濃度×接触時間
水道法・水質基準
水道法
- 専用水道 :給水人口100人または、1日最大給水量20m3を超える自家用水道
- 簡易専用水道 :水源が水道事業者のみで水槽有効容量が10m3を超えるもの
水質基準
- 大腸菌 :検出されないこと
- 一般細菌 :1mLの検水で、集落数が100以下
- 銅 :1.0mg/L以下
- 鉛 :0.01mg/L以下
- 色度 :5度以下
- 濁度 :2度以下
- 総トリハロメタン:0.1mg/L以下
水道施設
水道施設のフロー
取水施設 → 導水施設 → 浄水施設 → 送水施設 → 排水施設
浄水処理
- 浄水処理のフロー :沈殿 → ろ過 → 消毒
- 膜ろ過法 :浮遊物質の除去
- 臭気除去 :活性炭処理、オゾン処理
給水装置
排水管から分岐して設けられた給水管、およびこれに直結する給水用具
給水方式
受水槽方式と水道直結方式に大別
高置水槽方式
- 排水管 → 受水層 → 揚水ポンプ → 高置水槽 → 給水末端
- 給水圧力が一定
- 受水槽、高置水槽の2つの水槽があり、汚染の恐れが多い
- 高置水槽の水位により、揚水ポンプが起動と停止
- 受水槽の水位(減水警報水位)により、揚水ポンプの空転防止
圧力水槽方式
- 排水管 → 受水槽 → 給水ポンプ → 圧力水槽 → 給水末端
- 給水圧力が変動
ポンプ直送方式
- 排水管 → 受水槽 → 給水ポンプ → 給水末端
- 受水槽で受けてから、最下階で配管を展開し、上向き配管で給水
直結増圧方式
- 排水管 → 増圧ポンプ → 給水末端
- 受水槽がないので衛生的
- 一般的に、専用水道、簡易専用水道には用いられない
給水設備
上限水圧
- ホテル・住宅 :0.3MPa
- 事務所・商業施設:0.5MPa
最低必要水圧
- 一般水栓 :30KPa
- 大便器・シャワー:70KPa
- ガス瞬間湯沸器 :40~80KPa
1日当りの設計給水量
- 事務所 :60~100L/人
- ホテル客室部:350~400L/床
給水管の適正流速
- 0.9 ~1.2 m/s
- 上限は、2.0m/s
飲料用貯水槽
- 保守点検スペース :上部100cm以上、側面および底部60cm以上
- 流水間吐水部に、吐水空間を確保する
- FRP製は、紫外線に弱く、機械的強度も弱い
クロスコネクション
- 禁止
- 逆止弁は、クロスコネクションの防止にならない
- バイバスは、クロスコネクションの防止にならない
逆サイホン現象
逆サイホン現象とは、負圧により吐水した水が給水管内に逆流すること
ウォータハンマー(水撃)
- 弁を急閉すると、弁の上流側の圧力が上昇し、圧力が伝わる現象
- ウォータハンマー防止器は、発生箇所の近くに設置
- 水栓分離が起こりやすい部分は、ウォータハンマーが発生しやすい
鋼管の腐食
- アノード(陽極) :電流が流出する部分
- カソード(陰極) :電流が流入する部分
- アルカリ度の減少や塩化物濃度の上昇によって、水の腐食性は増加する
給水設備機器
- 渦巻きポンプ :速度エネルギーを圧力エネルギーに変換する渦巻きケーシングを備えた遠心ポンプ
- 弁 :玉形弁、仕切り弁、バタフライ弁、ボール弁
- フレキシブル継手 :配管の変位吸収のために設ける
給水配管
主な接続方法
- ステンレス鋼管 :溶接接合
- 銅管 :差込ろう接合
- ポリエチレン管・ポリプレン管 :融着接合
酸素濃度電池
- さびこぶ部(酸素濃度が低い部分):アノード(陽極)
- 管壁部(酸素濃度が高い部分) :カソード(陰極)
亜鉛メッキ銅管
さびが発生して赤水の原因となり、飲料水の配管材料としては不適
給水設備の汚染防止
- 飲料水用貯水槽は、六面点検できるように設置する
- 貯水槽の水抜き管は、貯水槽の最も低い部分から取り出す
- 大容量の貯水槽は、水の流れを水槽内で迂回させ、滞留水の発生を防止
- 大便器洗浄弁には、大気圧式バキュームブレーキを設置
貯水槽の清掃
受水槽 → 高置水槽の順で清掃
清掃後の消毒 :濃度50~100mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液などにより2回以上行う
清掃後の水洗いおよび水張り :清掃終了後30分以上経過してから
清掃後の残留塩素 :遊離残留塩素 0.2mg/L 結合残留塩素1.5mg/L以上
清掃従事者の健康診断 :6ヵ月毎
給水設備の管理
給水槽における残留塩素の測定
7日以内ごとに1回
赤水対策としての防錆剤
配管更新までの応急処置
負圧の発生
負圧は、ポンプ直送方式の上階で発生しやすい
ポンプの点検頻度と項目
- 毎日 :圧力、電圧、電流、軸受け温度、軸受け部の滴下状態
- 1回/1ヶ月:絶縁抵抗、各部の温度
- 1回/6ヶ月:ポンプと電動機の芯狂いなど
給湯設備
設計給湯量
- 総合病院 :150~250L/(床×日)
- ホテル宿泊部:75~150L/(人×日)
- 事務所 :7.5 ~11.5L/(人×日)
水中における気体の溶解度
温度が高いほど、圧力が低いほど、溶解度は小さくなる。
給湯加熱装置
- 直接加熱方式 :燃料や電気によって直接水を加熱する方式
- 間接加熱方式 :蒸気や温水を熱源として、加熱コイルなどで水を加熱する方式
- 貫流ボイラ :缶水量が少ないので、出湯温度が変化しやすいため、シャワーに不適
- 真空温水発生機 :缶体内は大気圧以下。労働安全衛生法のボイラに該当しない
- 無圧式温水発生機 :缶体内は開放(大気圧)。労働安全衛生法のボイラに該当しない
- 湯沸器 :貯蔵式ー開放構造・高温・飲用 貯湯式ー密閉構造
- 膨張管(逃し管) :途中に弁を設けない。補給水槽の水面以上に立ち上げる
給湯配管・循環ポンプ
給湯配管
- 給湯配管に銅管 :侵食防止対策で、1.2m/s
- 空気抜きのため、横管に1/200以上の勾配
- 逃がし管 :配管内の圧力が、設計圧力を超えると作動
- 流量の調整 :返湯管に設けた玉形弁などで調整
- 線膨張係数の比較 :金属管 < 樹脂管(架橋ポリエチレン管など)
- 伸縮管継手の伸縮吸収量の比較 :ベローズ(蛇腹)形 < スリープ(袖)形
循環ポンプ
- 位置 :循環ポンプは返湯管に設ける
- 揚程 :循環回路で最も大きくなる摩擦損失から決定
- 運転 :省エネ上は、返湯温度低下時のみ運転したほうがいい
給湯設備の管理
- 貯湯槽の給湯温度 :レジオネラ菌対策のため、常時60℃(最低でも55℃)以上
- 菌検出時の加熱処理:70℃程度の湯を20時間
- ワッシャ :細菌繁殖防止のため、天然ゴムよりも合成ゴム
- 圧力容器の検査:第1種ー1ヶ月以内に定期自主検査、1年以内に性能検査 第2種および小型圧力容器ー1年以内に定期自主検査
- 貯湯槽の電気防食 :流電陽極式ー犠牲陽極の状態を点検し取り替え 外部電源式ー電極の取替え不要。防食電流の調整。
- SUS444の方が、耐孔性、耐隙腐食性においてSUS304より優れている。SUS404は、水素脆化するので、電気防食はしない。
- 防錆剤の使用は、飲料水系と同様に配管更新までの応急処置
給湯循環配管の計算
Q=0.0143 × HL ÷ △T
- Q=循環流量[L/min]
- Hl =循環配管からの熱損失[W]
- △T=加熱装置における給湯温度と返湯温度の差
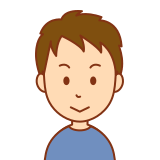
0.0143はカロリーをワット変換するためです。
雑用水設備
雑用水の維持管理
| 基準値 | 検査周期 |
| PH値 :5.8以上 8.6以下 | 7日以内ごとに1回 |
| 臭気 :異常でないこと | 同上 |
| 外観 :ほとんど無色透明 | 同上 |
| 大腸菌 :検出されないこと | 2ヶ月以内ごとに1回 |
| 濁度:2度以下(水洗便所用水は除く) | 同上 |
- 雑用水設備からの汚泥は産業廃棄物
- 色度・臭気の除去 :活性炭処理法
- 塩素消毒効果に影響 :水温、接触時間、残留有機物量、スライム等の藻類
- 雑用水受水槽 :二重スラブ内ではなく、六面点検可能なように設計
循環方式
- 個別循環法式 :同一ビル内で処理し、雑用水用として利用
- 地区循環方式 :共同で雑用水道を運営し、地区内の雑用水として利用
- 広域循環方式 :下水処理場等で処理された水を、地域内の雑用水として利用
排水再利用施設
生物処理法
→ スクリーン→ 流量調整槽→ 生物処理槽→ 沈殿槽→ ろ過装置→ 消毒槽→ 排水処理水槽→
膜分離活性炭処理法
→スクリーン→ 流量調整槽→ 膜分離装置→ 活性炭処理装置→ 消毒液→ 排水処理水槽→
SS(浮遊懸濁物質)の低い排水処理に適している
雨水処理設備
→ スクリーン→ 沈砂槽→ 雨水貯留槽→ 消毒装置→ 雨水処理装置
排水トラップ
- 排水トラップの深さ :ディップからウェアまでの垂直距離は、50mm 以上100mm以下
- サイホン式トラップ :Pトラップ、Sトラップなど
- 非サイホン式トラップ:わんトラップ、ドラムトラップ
- トラップの排水強度 :(封水保持能力) サイホントラップ < 非サイホントラップ Pトラップ > Sトラップ
排水設備
排水横管の最小勾配
| 管径(mm) | 勾配 |
| 65以下 | 最小 1/50 |
| 75、100 | 最小 1/100 |
| 125 | 最小 1/150 |
| 150以上 | 最小 1/200 |
排水設備の要点
- 排水立て管の管径 :上部と下部は同径
- オフセット部(移行部)の上下 :600mm以上は、排水横枝管を設けない
- 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 :肉厚が薄いのでネジきり不可。メカニカル式の排水鋼管用可とう継手を用いる
- 飲料用貯水槽の間接排水 :150mm以上の排水口空間を確保する
- 掃除口の設置関係 :30m以内。 ※管径100mm以下の場合は15m以内。
- 掃除口の大きさ :管径100mm以下は管径、管径100mm超は100mm以上
- 雨水排水ます :20mm程度の流入管との管底差。 150mm以上の泥だめを設ける
- 汚水排水ます :槽(インバート)を設ける
通気設備
伸頂通気管方式
- 伸頂通気管で構成され、通気立て管のない方式
- 排水横主管が以降が、満流になる場合は採用しない
特殊継手システム
- 単管式排水システムともいう
- 伸頂通気方式の一種
- 排水横枝管の接続部の少ない集合住宅に用いられる
結合通気管
- 排水立て管と通気立て管を接続
- 排水立て管の圧力緩和のため設ける
伸頂通気管
排水立て管の頂部を、管径を縮小せずに大気に開口する
通気弁
空気の吸入だけを行い、空気の排出はしない。
正圧防止にはならない。
通気管の接続
- 通気立て管と伸頂通気管 :最高位の器具のあふれ線より150mm以上高い位置
- 通気立て管の下部と排水立て管 :最低位の排水横枝管より低い位置
- 各個通気管と器具排水管 :トラップウェアから器具排水管の管径の2倍以上離れた位置
- ループ通気管と排水横管 :最上流の器具排水管と排水横管の接続部のすぐ下流
排水通気設備の管理
汚水槽、ちゅう房排水槽の水位制御
- 電極棒ではなく、フロートスイッチを用いる
- 長時間の滞留による腐敗を防止するため、ポンプの運転停止位置は低くする
- 滞留による腐敗を防止するため、タイマーにより2時間程度でポンプにて排水
排水槽の清掃
- 高圧洗浄法 :5~30MPaの水を噴射して洗浄
- ウォータラム法:圧縮空気により閉鎖物を除去、固着したグリースは除去できない
- スネークワイヤ法:長さ25mまでの排水横管の清掃に用いる
- ロッド法 :手動で排水管内に挿入して清掃。 最大30m程度。
- 6ヶ月以内ごとに
- 作業前に酸素濃度18%以上、硫化水素濃度は10ppm以下を確認
- 作業用照明は、メタンガス等に引火しないように、防爆型とする
排水ポンプの点検
- 絶縁抵抗測定 :1ヶ月に1回程度。 1MΩ以上。
- メカニカルシールのオイル交換 :6ヶ月~1年に1回程度
- メカニカルシールの交換 :1~2年に1回程度
- オーバーホール :3~5年に1回程度
グリース阻集器の清掃
- ちゅう介の除去 :毎日
- グリースの除去 :7~10日に1回程度
- トラップの清掃 :2ヶ月に1回程度
- グリース阻集器からの廃棄物は、産業廃棄物
衛生器具
衛生器具設備
- 水受け容器 :使用した水を排水系統に導く器具
- あふれ線 :衛生器具~オーバーフローロではなく上線 開放式水槽~オーバーフローロ
衛生器具設備の定期点検
- 大便器、小便器 :取り付け状態(半年に1回)・排水状態(半年に1回)
- 洗面器 :取り付け状態(2ヶ月に1回)・排水状態(半年に1回)
- 洗浄タンク・洗浄弁 :詰まり、汚れ(半年に1回)・水量調節弁(半年に1回)
- 事務所に設置する便器の必要個数は、事務所衛生基準規則に規定
大便器と小便器
大便器
- 洗い落とし式 :落差を利用
- サイホン式 :サイホン作用を利用
- サイホンゼット式 :溜水面が広い
- ブローアウト式 :噴出作用。排水口が壁面。音が大きい。
- 1回当りの水量 :節水1型(8.5L以下) 節水2型(6.5L以下)
- サイホン式便器の溜水面が小さい場合の原因:補助水管がオーバーフローロ管に差し込まれていない
小便器
- 手動式小便器 :公衆用には適さない
- 小便器のトラップ:公衆用には清掃しやすい着脱式が適している
阻集器の種類と用途
- グリース阻集器 :ちゅう房
- オイル阻集器 :駐車場、洗車場
- ブラスタ阻集器 :歯科技工室、ギプス室
- 毛髪阻集器 :浴場、プール
- 砂阻集器 :工場など
ちゅう房排水除害施設の油分の浮上速度
- 排水の粘性に反比例する
- 粘性が大きくなると、遅くなる
- 油粒子の直径が大きくなると、速くなる
排水槽・排水ポンプ
- 排水槽の底部の勾配 :1/15以上 1/10以下
- 排水槽のマンホール :直径600mm以上の円が内接できるもの
- 排水ポンプ :吸い込みピットの壁などから200mm以上離す
- 湧水槽のポンプ起動の高水位は、二重スラブの底面以下とする
雨水排水設備
- 雨水排水系統は、単独系統として屋外に排水する
- 雨水立て管と排水立て管は、兼用してはならない
- ルーフドレンのストレーナ間の面積:雨水立て管の2倍以上
排水の水質
- BOD :生物化学的酸素要求量。20℃で5日間に微生物によって消費される酸素量。
- COD :化学的酸素要求量。酸化剤によって消費される酸素量。
- SS :排水中に浮遊するけんだく物質
浄化槽
- 生物膜法 :担体流動法、回転板接触法、接触ばっ気法、散水万床法
- 活性汚泥法 :長時間ばっ気法、標準活性汚泥法
- 消毒剤の溶解速度: 無機系塩素剤 > 有機塩素剤
- 浮遊性の有機物質の除去:急速砂ろ過法、擬集沈殿法(リン化合物など)
浄化槽の管理
- 最初の保守点検は、使用開始直前に行う
- 指定検査機関の水質検査:使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間
- 放流水BOD濃度の基準値 :20mg/L以下 ※BOD~生物化学的酸素要求老
活性汚泥放
- 点検回数 :1週間に1回
- 汚泥容量指標(SVI):沈殿汚泥1gが占める容積 [mL]
浄化槽の点検内容
- 沈殿槽 :スカム・堆積汚泥の生成状況
- 嫌気ろ床槽:スカム・堆積汚泥の生成状況
- ばっ気槽 :MLS濃度、溶存酸素濃度
浄化槽の計算
BOD除去率
BOD除去率=(流水量のBOD濃度[mg/L]–放流水のBOD濃度mg/L[]) / 流入水のBOd濃度×100[%]
BODの容積負荷
- 1m3当りの1日に流入するBOD量
- 単位は、kg/(m3×日)
下水道
下水道の要点
- 合流式 :汚水と雨水が合流
- 分流式 :汚水と雨水が分流
- 流域下水道 :2つ以上の市町村にまたがる。 事業主体は都道府県。
水質汚濁防止法の特定施設(主なもの)
- 旅館業の用に供する施設で次のもの、ちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設
- 飲食店に設置されるちゅう房施設(総床面積420㎡は除く)
- 病院で病床数が300以上に設置される次のもの、ちゅう房施設、洗浄施設、入浴施設
ガス設備
- 都市ガスの供給圧力 :低圧(0.1MPa未満)、中圧(0.1MPa以上1.0Mpa未満)、高圧(1.0 MPa以上)
- ガバナ :ガスの圧力を所定の範囲内に調整する整圧器
- ヒューズガバナ :大量のガスが流れた時、自動的に停止
- マイコンメータ :震度5強で自動遮断
- ガスの理論空気量 < ガスの理論排ガス量
消火設備
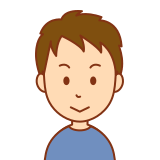
この項では、消防設備士6類の基本問題の類似問題が出題されることが多いです。
消防設備点検
- 機器点検 :6ヶ月に1回(作動点検、機能点検、外観点検)
- 総合点検 :1年に1回
屋外消火栓設備
公設消防隊が到着するまでの初期消火
連結送水管
公設消防隊が使用する消防隊専用栓
泡消火設備
油火災用、駐車場等。 窒息、冷却効果。
スプリンクラー設備
開放型 :手動開放により散水。舞台部に設置。
閉鎖型 :ヘッドの感熱部が分解して放水
閉鎖型湿式 :ヘッドに常時、水が充填
閉鎖型乾式 :ヘッドに常時、圧縮空気が充填。凍結防止。
閉鎖型予備動作式:感知器とベッドの連動で散水。水損防止。
不活性ガス消火設備
- 希釈作用
- 電気室、ボイラ室など
粉末消火設備
負触媒作用
金属火災
Mg やNaなど酸素と反応しやすい金属の火災
このぺーじのまとめ
- 給水・排水の分野は、普段の仕事で知っておいたほうがいい事が多い
- 出題数も多いので、高得点を狙いたい
- 過去問を繰り返すことで、なんとかなるはず
読了、ありがとうございました
また、どこかで・・・